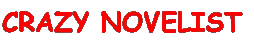  私自身が丹精を込めて書き上げた小説を披露するサイト 私自身が丹精を込めて書き上げた小説を披露するサイト |
| ・HOME・ ・BACK NUMBER・ ・CONTACT・ ・スマホ用サイト・ |
|
|
|
猫の子町
筆名 出雲 隼凱
渡航(其の1)
巨大な成田空港の第二ターミナルのロビーに入ると、外では強い風のせいでそれ以外の如何なる音も聞き取れなかった耳が信じられない程他の利用客の声に鋭く反応した。その風の音は完全にシャットアウトされてはいたがロビーの内側から窓を通して見える外の景色が薄っすらと土埃でぼやけているのがその強さを物語っていた。たまに紙切れがその土埃に混じって行き場所を心得ているかのように空間を横切っていった。ロビーに入ってくる女の旅行者の中には髪の毛を片手で押さえている女も何人かいた。頭に被せた小さな帽子を手で押さえている子供もいた。
思った通り空港は空いていた。山瀬はゆっくりチェックインしようと思っていた。いつもなら浮き浮き気分で直ぐにチェックインを済ませなるべく自分の好きな席を指定するのだが、恐らく自分の搭乗する機が満員のはずはないという予想の基に只々だらだらと不貞腐れた子供のように空港の中を散策していた。そうしてようやくチェックインカウンターへ出向いた。
当然のこと席を指定することは出来なかったが、離陸した後に席を移ればいいではないかと自分を慰めていた。ボーディングパスを見ると明らかに翼から後ろ側の席だった。山瀬は以前友人から飛行機が事故にあったとき後部座席は死ぬ確率が高いと聞かされそれを信じていた。それに翼より前の席なら飛行機のエンジン音が少しは気にならなくなることを知っていた。実のところ山瀬は飛行機が苦手だった。飛行機酔いはしないのだが、何百人という人間をその緊張感と一緒に乗せて飛ぶ飛行機が異常に大きな棺桶のように感じられて嫌だった。今回の旅は緊張感の他に自分の不安感も一緒に合わせて棺桶に押し込まれるのも山瀬のチェックインを遅らせた原因になっていた。
まばらになった待合ロビーには静けさが漂っていた。ゆっくりと立ち上がり、飛行機の出発時間直前に搭乗した山瀬は乗客の発する熱気に驚かされた。山瀬の予想は確実に外れていた。
「なんだ結構いるなあ…」
安い航空券を狙った旅行者や帰省の人たちが重なったらしい。座席に対して99%くらいの搭乗客が乗っているように見えた。要するに満員の状態だった。さっきチェックインカウンターで席を指定できなかった訳がこれで納得できた。
山瀬は飛行機が飛び立つ前から気疲れしてしまっていた。自分の席を見つけると軽い手荷物を座席の下に無理やり押し込み腰を下ろした。通路側の席に座れたことだけが山瀬の唯一の救いだった。トイレに行くときに寝ている隣の乗客を起こすのは誰にとっても気の引ける行為だ。それについては山瀬も例外ではなかった。山瀬もそれを心得ているので通路側に座ったときは、逆に窓側に座っている他の客に気を使ってなるべく目を閉じないようにしていた。今回はそれに当てはまった訳だ。とりあえず座席ベルトを締めて飛び発つ前の緊張のひと時を味わっていた。
風はまだ強かったが飛行機が離陸できない程のものではなく、しばらくしてから山瀬たちを乗せた機は上空でほぼ地面と平行に飛び始め、頭の上で光っていたベルト着用のマークもポーンという軽い音と同時に光を放たなくなった。乗客皆の緊張がほんのちょっと和らいだせいか、機内のあちらこちらで話し声がしていた。
「今回はどちらへお出かけですか」
山瀬の左側の席に座っている中年の男がふと声を掛けてきた。頭には白い髪のほうが黒いそれよりも多く混じっていた。丸顔にほんの少し大きめの眼とその両脇にできた小さな皺が男の与える印象を柔らかくしていた。歳は50歳過ぎくらいだろうと山瀬は思った。こういう閉ざされた緊張感の漂う空間に閉じ込められると、誰しも他人との会話が恋しくなるものだ。以前山瀬はおかしなことを考えたことがあった。もしこの大きなジャンボジェットにパイロット以外に自分だけしか乗っていなかったら、恐らく飛び立つ前に自分は降りてしまうのではないか…と。いくら短時間の飛行であったとしてもこの緊張感を分かち合う乗客が誰一人いない飛行機なんてまっぴらだ。それ故に、山瀬にとっても機内で話しかけられるというのは全くと言っていい程苦痛ではなかった。
「カミギン島まで行ってこようと思ってます」
山瀬の口が素直に男の問いに答えていた。
「そうですか。私はパラワンなんですよ…。会ってすぐの貴方にこんなことを言うのも何なんですがね、実は不幸ができてしまいましてね…」
こういう空間の中ではこういった不自然な会話が当たり前のように通用てしまう。この緊張感に満たされた閉ざされた空間以外で初めて会った赤の他人にいきなり不幸の話をする人間なんて恐らく皆無だろう。ただこういった状況下でこのような不自然な会話が起きてしまうことについても以前山瀬が考えていたことのひとつだった。不確実な死に対する恐怖感から来る告白のようなものなのではないかと山瀬は考えていた。山瀬にとってはこの不自然な会話もこの空間だけでは大いに有り得ることだった。いや、なければならないことだとも考えていた。
「そうですか。それは大変ですね。奥様のご家族が亡くなられたんですか」
日本人男性とフィリピン人女性が国際結婚をしている例は少なくはない。フィリピン人と日本人のごく普通の男女関係を知るごく普通の日本人だったらそう考えるのが当たり前のように、山瀬のその男に対する質問も的を射たものだった。ただ、たまに例外もあるものだ。男は少し考える時間を置いた。
「いえ、実の従兄弟が死んでしまいまして…」
山瀬は面食らった。たまたま隣り合った乗客が、内容はほんの少し違ったにしろ、同じような原因で旅をさせられているということに驚かされていた。ただ、山瀬の場合はあくまでも自殺の調査を依頼されているだけの身分だったので、見ず知らずの男にあっけらかんとそれを話すことは避けようと思った。機内食を食べ、その後ビールを飲んでいる間も山瀬はその男と軽い会話を交わしていたが、そのうち男は疲れたらしく目を閉じてしまった。
飛行機がマニラ・ニノイ・アキノ国際空港に吸い込まれるまで男は目を閉じていた。山瀬は男の顔をチラッと見ながら、幾田優子が考えているように、この男も自分の肉親の死に何か疑問を感じているのではないだろうかという思いに捉われていた。
「それじゃ、お気をつけて…」
山瀬は男にそう言い残して席を立ち先を急いでいる乗客に混じって飛行機を降りた。
空港に漂う空気の臭いが成田空港のそれとは違っていた。この国を真っ先に鼻で感じるのは自分だけだろうかと心の中で笑っていた。山瀬は腹いっぱいそのココナッツのような甘い香りを含んだ空気を吸い込んでみた。またフィリピンに来たんだなという感覚が山瀬の腹を満たしていった。
前話へ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|