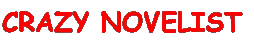  私自身が丹精を込めて書き上げた小説を披露するサイト 私自身が丹精を込めて書き上げた小説を披露するサイト |
| ・HOME・ ・BACK NUMBER・ ・CONTACT・ ・スマホ用サイト・ |
|
|
|
猫の子町
筆名 出雲 隼凱
首輪(其の1)
気がつくと眠りに落ちる前と同じうつ伏せの状態だった。眠りに落ちる前と違っていたのはさっきまで部屋に入ってきていた淡い陽の光が、その明るさを半分以下に落としているということだけだった。ふと壁に掛けられている時計に目をやると既に5時を回っていた。部屋の暗さからしてそのくらいだろうと思った。約3時間寝たことになる。そのことが山瀬を驚かせていた。山瀬は急に空腹感に襲われた。
「そういえば昼飯食ってなかったな」
昼の食事を忘れてしまうのは山瀬の癖で、時にはわざと昼食を省略してしまうことがあった。夕食を食べてしまうにはまだ早いと思った山瀬は海岸を散歩してみることにした。1階に降りてカウンターの中を覗いてみるとアイリーンが伝票のようなものを纏めているところだった。山瀬は部屋の鍵を手渡しながら海岸までの道筋を訊いてみたが、あまりにも理解し難いアイリーンの道案内に頷くことしか出来なかった。
「後でご飯食べに来るよ」
ひとこと言い残し薄暗い道を海の方向に歩き出した。ほんのり潮の香りを含んだ風が山瀬の身体のあちらこちらをくすぐった。海岸まで出るのにほんの少し手古摺ったが、それでも何とか辿り着くことが出来た。
海は昼に港に到着したときと同じように殆どと言っていい程波は無かった。ただ全く波打っていない訳ではなく小さな波が波打ち際でパシャーンパシャーンと小さな音を立てていた。それがなければ静かな湖の畔にでもいるかのような錯覚に陥るくらい波はなかった。山瀬は、警察へ行って話しを聞いてみるか、それともまず小町の家に行ってみようかと明日からの自分の行動をあれこれと頭の中で検索していた。警察は検死までしているのだから小町の自殺について既にもう何の疑いも持っていないだろう。新聞記事に書かれていた通り地元の人たちから何の手掛かりも得られなかったのだから、情報を得られるとすれば小町の遺体を検死した検死官の話だけだ。小町の自殺前の行動を知り得るのならば恐らく小町の家の近所の人たちに話を聞くべきだ。ただどちらにしてもその両方に足を運ばなければならなくなるだろう。歩きながらそんなことを考えているうちに辺りは見通しが利かなくなる程暗くなっていた。
「戻って晩飯でも食うか」
今来た道を戻りながら山瀬の歩調は空腹のせいか来たときのそれと比べてほんの少しだけ速くなっていた。増してやここは日本ではない。あまり暗くなった道を無闇に外国人が歩かないほうが身のためだということを山瀬はよく心得ていた。
サミス・インに戻ると既にカウンターにアイリーンの姿はなかった。その代わりに経営者の女房というような風情の女がカウンターで山瀬を出迎えた。
「こんばんは」
対応の仕方で経営に関係している人間だというのがすぐ分かった。挨拶なんてしてくるウェイトレスは稀だからだ。増してや彼女が身に着けている服がさっきまでカウンターにいたアイリーンのそれとはかけ離れていたことから、山瀬はこの女がサミスの妻なのだろうと勝手な想像をしていた。サミスなんて名前の女と山瀬はこれまで出会ったことがなかった。サミスは確実に男の名前だという先入観念が山瀬にはあった。この時もその先入観念が働き、目の前にいる女は経営者であるサミスの妻なのであろうという結論に行き着いた。彼女は髪の毛を腰の辺りまで伸ばしていて、毛先を何かに引っ張られているかのように真っ直ぐ地面に向かって下ろしていた。細長の顔についた少し大きめの目が優しい印象を山瀬に投げかけていた。
女はキーボックスから鍵をひとつ取り出すとこちらへ向き直った。そしてそれをカウンターの上に乗せた。
「こんばんは。何か食べたいんですが。お奨めの料理はありますかね」
とりあえず鍵を受け取りながら、山瀬はそう訪ねた。208号室の鍵を渡された山瀬は気の利いたこの女の行動に関心した。山瀬は部屋の番号を言った覚えはなかった。
「豚肉の煮込み料理はいかがでしょう」
山瀬はカウンターに腰を下ろすことにした。この女から何か情報を得られるのではないかと思ったのだった。
「じゃあそれとライスとビールを一本ください。ビールは先にください」
腰を下ろしながらそう言うと彼女は早速冷蔵庫からビールを一本取り出し山瀬の目の前に差し出した。よく冷えているビールだった。食事を注文して出来上がるまでの間ビールを飲むのが山瀬の外食の仕方だった。食事が早めに出てきたときはそのおかずをつまみにする。遅めになったときはもう一本ビールを追加して飲むのが彼なりの決まりだった。今回は食事が早めに出てきた。煮込み料理なので既に煮てあったものを温め直したのだろう。ただ彼女からどんな小さな情報でも得たい気持ちの山瀬は少しゆっくりめにビールとその煮込みを口に運んでいた。カウンターの中の彼女はやっと仕事がなくなったらしく定位置について腰掛けていた。山瀬が飲んでいた小瓶のビールも丁度底を突いていた。
「もう一本ください」
山瀬は2本目のビールを飲み始めると、心地よい酔いが頭の中を刺激し始めた。
「ちょっとお訊きしても構いませんか。最近自殺した日本人の女の人のことんなんですけど...」
彼女は何気なく立ち上がり山瀬とカウンターを挟んだ。扇風機のふんわりとした風に長い髪がほんの少しだけ揺れているのが印象的だった。
「ああ、小町のことですね。彼女だったらうちにも何度か食べに来ていましたよ」
こうも簡単に糸口が見つかると思わなかった山瀬だったが、島の大きさを考えてみるとこれも当然のことかもしれないと思った。この小さな島で小町が生活していたことを想像すると、小町がこのレストランに来たことがないということの方が考え難いことだろうと山瀬は思った。
「いつも1人で食べに来ていたんですか。それとも誰か一緒に来た人がいたとか...」
山瀬は一口ビールを口に運んだ。彼女は何か得体の知れない動くものを目で辿るように視線を中空に向けて記憶を追いかけているようだった。
「いいえ、いつもひとりでした…。そういえば一度だけ電話で何か言い争っていたようなことがありました。ただ日本語で話しているようだったから私には全く意味が分かりませんでしたけど…、その後支払いを忘れて出て行きそうになった小町を私が引き止めたのを覚えています」
電話というのは携帯電話のことだろうと山瀬は思った。携帯電話から小町の交友関係が分かるかもしれない。ちょっとした情報の糸口を得られたような気がした。
「いつ頃のことだか覚えてらっしゃいますか」
「最近のことよ」
山瀬は2本目のビールを飲み干し、残った料理をすべて平らげた。小町が自殺する前にやはり何かがあったのだと山瀬は思った。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|