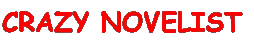  私自身が丹精を込めて書き上げた小説を披露するサイト 私自身が丹精を込めて書き上げた小説を披露するサイト |
| ・HOME・ ・BACK NUMBER・ ・CONTACT・ ・スマホ用サイト・ |
|
|
|
猫の子町
筆名 出雲 隼凱
首輪(其の3)
雑貨屋の女に言われた通り海沿いの道を気休めの潮風に吹かれながら再び歩き始めた。山瀬はたまに海の方に目を向けながらその濃い青色と薄い水色のコントラストを楽しんでいた。そうしないと熱さを紛らわしきれなかった。熱気が路面から湧き上がり山瀬の顔に覆いか被さってきた。汗は相変わらず蟻のように額や頬を伝って下の方に歩いていった。
襲いかかってくる熱さを除けば小町の家は然程苦労せずに行き着くことができた。高台の方に上がっていく坂道がひとつしかなかったことが幸いしたのだろう。海沿いの道を折れて少し坂を登ったところに小さな広場があった。ぼろぼろの板とぼろぼろのネットを組み合わせて作ったバスケットボールの投的板が一つ置かれていた。流石にこの時間帯にバスケットボールをしている子供達はいなかった。道に覆い被さるように大きなアカシアの木の枝が張り出して大きな陰を作っていた。その陰の下に置かれたベンチに初老の男が座っていた。
「おじさん、この辺に日本人の家ってあるかな…」
無口なのか、それとも驚いているのか男は一言も口に出そうとはしなかった。しかし男が持ち上げた右手の先についている人差し指が静まり返った一軒の家を指差していた。何となく気まずく感じた山瀬は礼だけを言ってその場を離れた。
その家はベンチの置かれた広場と道を挟んで反対側に建っていた。その家が醸し出す何かひっそりとした静けさのようなものがそれが小町の家だということを物語っていた。窓は締め切られ、その全てにカーテンが引かれていた。玄関のドアも来るものを拒むかのようにその口を硬く閉ざしていた。玄関のドアに近寄った山瀬は約束事のようにドアをノックしてみた。当然返事など期待してはいなかった。ただそれが礼儀のような気がしてそうせざるを得なかった。ノックが誰もいない締め切られた家の中に響いていた。まだ確実に小町の家だと判った訳ではないが山瀬の胸の中にほぼこの家が小町の家だったいうことが染み込み始めていた。思った通り返事はなかった。
ふと背後に人の気配を感じた山瀬は少し驚いて後ろを振り返った。小太りで眼の大きい女が箒を片手にそこに立っていた。
「何か…」
女はそう短く声を発すると、後は貴方が話しなさいと言わんばかりに黙っていた。何か悲しいものに引き込まれていた山瀬は無理やりに引き戻されたような気がして、呆気に取られて答えが直ぐに出てこなかった。
「あなたもしかして日本人ですか」
言葉を詰まらせている山瀬より先に女が静かに質問した。
「え、ええそうです」
山瀬は、彼が小町の母親幾田優子から依頼されて小町の自殺の件について調べにここまでやってきたことを説明した。
「そうですか。本当に残念です。何で自殺なんてしたのか…」
女も名前を山瀬に告げ、自分が小町の身の回りを世話していたことなどを簡単に山瀬に説明した。女はマリーという名前だった。山瀬は返す言葉が見つからなかった。ふと下を見ると黒と白の毛色をした猫がマリーの足元に絡みついていた。
「私の家で話しませんか」
そう短く静かに呟くとマリーは山瀬の答えを待つことなく彼女の家の方へ向き返って歩き出した。山瀬にとっても小町の身の回りの世話していたマリーの話を聞くことができるのは都合が良かった。さっきまで気休めだった潮風が勢いよく坂道を駆け上がってきた。ほんの一瞬だが山瀬はその風に後押しされているような感覚を覚えた。
マリーの家はこの島で見られる殆どの家と同じようにブロックを積み上げてその上にトタン屋根を乗せただけの中途半端な造りだった。家の裏側にある勝手口から彼女は中に入っていった。山瀬もマリーの後に続いた。中に入ると、急に暗がりに入ったせいか分からなかったが、目が暗さに慣れてくるとそこが台所だということが分かった。
「桃ちゃんお腹空いてるの。じゃあ何かあげようか」
猫も一緒についてきていたようだ。マリーはしつこく足元に絡み付いてくる白黒の猫に向かって話しかけると、台所の端の方から餌のようなものを取り出して床に置いてある器に入れた。
「この子、小町が日本から連れてきた猫なんですよ。すごく可愛がってました。まさか自殺してしまうなんて」
マリーの目は微かに潤んでいた。
「何か特別考え込んでいるようなことはありませんでしたか。小町さんのお母さんはどうしても彼女の自殺に納得ができないようで、それで私に調査を依頼したみたいなんです」
マリーの左眼からひと粒の涙が頬を伝った。それを直ぐに左手の甲で拭うと2回鼻を啜った。
「私もそれなりに彼女が自殺する前のことを振り返って考えてみるのですが全く思い当たりません。いつものように何の変わりもなく猫達と戯れてましたし…」
猫はマリーのくれた餌を平らげた後まだ物足りないのか再びマリーの足元に絡み付いていた。山瀬は結局のところ何の情報も掴めないのかもしれないと頭をポリポリと掻き始めた。その山瀬の動きに反応したかのように猫がマリーの足元で動きを止めた。山瀬の方に顔を向け何か言いたいような目つきをしている。
「この猫メスなんですか」
猫の視線を感じた山瀬の興味が小町の事件から逸れ、何の意味もない質問になって口から出てきた。
「そうです。この子はメスなんですが、この子の他にも2匹のオスともう2匹のメス合わせて5匹の猫を日本から連れてきたんです」マリーはそう答えながら猫を持ち上げると膝の上に抱きかかえるようにして座った。
「小町の話だとこの子もうかなりの歳みたいなんです。飼い始めてから13,4年経っているって言ってました」
山瀬の興味がまた小町の事件に引き戻された。
「そうなんですか。そんなに長く飼っている猫を置き去りにして行くなんて私には考え難いことです。いったい小町さんは何を考えていたのかな」
マリーは猫の首元を無心で撫でていた。そのマリーの仕草によって会話が中断されてしまった。何を思ったか猫が急にマリーの膝から飛び降りて山瀬の足元に絡み始めた。
「なんだいお前。俺は食べ物なんか持ってないよ」
もともと動物が嫌いでない山瀬はマリーがしたのと同じ様に自分の膝の上に猫を乗せた。猫を抱くと殆どの人がするように山瀬も同じ様に無意識に喉元をゆっくり撫でていた。つけられた真新しい赤い首輪に喉元を撫でる指が引っかかるのが山瀬をほんの少し苛つかせた。よく見るとその首輪にはカッターで傷付けたような角ばった文字で「CC」と書いてある。
「この首輪、貴方が付けてあげたんですか」
「いいえ。小町が自殺する前に付けてあげた物だと思います」
「そうですか。新しい首輪だからてっきり貴方が付けてあげたのかと思いましたよ」
山瀬は猫の首輪を右手の人差し指でほんの少し撫でてみた。真新しさが指に伝わってきた。ほんの小さな間ができたがマリーが先に口を開いた。
「家の中も見てみますか…」
山瀬はマリーの言葉に小さく頷いて見せた。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|